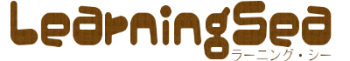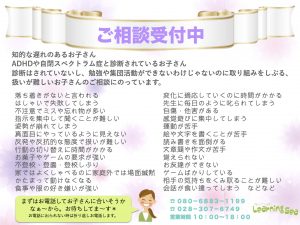✨認知症を理解し手立てを見つける【結びとプロジェクト】スタート✨
県内の高齢者の方のためのグループホームで、認知症のさまざまな課題を解決する関わりに取り組んでいるところがあります。
全てのグループホームがもちろんそうなのです。
ただこちらのグループホームでは、【自閉症の方との関わり】から学んできたことを認知症の方のさまざまな場面で役立てられています。
例えば・・・
*行動に注目すること
*短期的にどうにかするのではなく1年、2年と時間の長期的な見通しを持つこと
*視覚的な手がかりを提供すること
1月にこのグループホームの取り組みを聞いてとても感動しました。
このグループホームの取り組みがどうしていい結果をもたらしたのか?
問題となる行動を変えることができたのか?
いくつか仮説は持ちましたが、より詳しく知りたいと思いました。
これから高齢者の方、認知症の方が増えることを考えると、認知症の方への関わりに現実的な手立てを持つことは役立つはずです。
なぜならばご家族の中に認知症の高齢者の方がいたら、働き盛りの40代、50代、60代の方の負担が大きくなり、社会的に活躍することが難しいです。
認知症の方の問題はさまざまで、全般的な生活を大きく左右します。
外出したがる、帰りたがる、入浴やケアを拒否する、妄想や被害的な観念が強くなる、眠らないなどなど。
とても感情的になりもするので、関わることに消耗してしまうのです。
お互い困らせようとしているわけではないのですが、どうしても感情的な ざわざわチクチク、イライラが募ります。
理解し合えないことの苦痛が降り積もっていきます。
認知症の課題は社会を大きく変えるように思います。
昨日は、グループホームにお邪魔しまして、所内でテーマになっていることを一緒に考えました。
これはきっと他のところでもよくあることです。
でも日常のせわしない業務の中でどうやってその方の行動への理解を深めていくかはとても大変なことです。
今年度は、月1回訪問してケース・カンファを中心にした職員研修をしながら楽しくさまざまなテーマに取り組んでいく研修をすることになりました。
所長さんはもちろん、職員さんも熱心で一緒に話しているとワクワクします。
私の提案を聞いて意見をくれて、さらに練り上げていくことができるのでとてもやりがいがあります。
私は認知症の方の関わり方も、どんなことでこじれやすいかも知らなかったので、職員の皆さんに教えてもらうことがたくさんあります。
お互い学びあいながら、認知症について理解を深めていきます。
私の大きな役割はケース・カンファを通して、職員皆さんの取り組みをちゃんと評価していくことです。
職員の皆さんが自分たちの取り組みに自信を持って主体的に考え工夫し、仕事を楽しんでくれることが日々の自主的な研鑽につながり、一人一人の進化に貢献すると考えています。
認知症の方への関わりは、職員間のチームワークが50%を占めるかもしれませんね。
打ち合わせはあっという間に3時間経ってしまいました。
今月のケース・カンファとプチ・ワークショップの内容も決まり、ほくほく嬉しい気持ちで帰宅しました。
美しい田園風景と花々、緑の風景をドライブしながら帰るのはとても心地よかったです。
素敵な方々と仕事を共にできることに感謝します✨
 田んぼが海のように見えます。
この風景との出会いに感謝✨
田んぼが海のように見えます。
この風景との出会いに感謝✨
 田んぼが海のように見えます。
この風景との出会いに感謝✨
田んぼが海のように見えます。
この風景との出会いに感謝✨