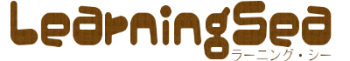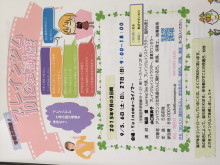「性同一性障害GID」かもしれない子どもへのサポート
幼児期の相談は、いろいろな子と接するということなんだなと改めて思いました。
直接お会いしてはいないけど、保健師さんから相談がありました。
どんなふうに彼らを支えられるだろうか?
女の子らしさのある男の子について、考えたことをまとめました。
1. GIDかどうかは、長期的に見ていけばよい
本当にGIDなのか、とそうだとするならこう、そうじゃないならこう、と大人は右往左往しがちです。
今の好みや関心は女の子らしいものに向いています。
今の状態像としてはGIDととらえて育てることが、本人を尊重する大人の関わりです。
本人の好みや関心を否定することは、本人を否定することになります。
本当に本人が女の子の格好が嫌になったら、この子は絶対「嫌、着ない!」って言いますよね。
もしそう言ったら、そのときに違う扱い方に変えたらいいのです。
2. 子どもを守る
GIDの方は、周囲から「おかしい」、「なんで男なのに女みたいな服を着るの?」など、率直な、あるいは批判的な言葉かけをなされやすいことから、自傷・自殺企図などが多いでしょう。
ご家族が本人を守ることが大切です。
周囲の関わりに注意を払ったり、友達関係の情報収集が必要です。
3. 周囲が家族を守る、みんなで育てる
ご家族も社会的に追い詰められるからこそ、ご家族が本人を責めます。
ご家族が追い詰められないように、みんなでこの子を見守り育てましょう。
「ご家族のせい、お母さんのせいでこうなったわけではないです」、ということを繰り返しお伝えします。
ご家族はこのことを、何度も打ち消してはまた考えてしまうものですから、繰り返し繰り返し言葉にして伝えます。
他のお子さんより手間かけて育てましょう。
本人を理解し、仲間として受け入れることは、社会的な豊かさを享受することにつながります。どの子にとっても自分らしさを大事にすることがどんなに素晴らしいかを学び、自分を大切にすることにつながります。
この子をみんなが大切にする大人の姿を見て、周囲のお子さんも「一人ひとり」を大切にすることを実体験として学びます。
周囲の接し方が、他の子どもへの模範(モデル)となります。
大人が普通に関われば、他の子どもも普通に接します。
4. 現在のお母さんのやり方を支持します
お母さんが理解して本人の好みの服装を着ることを見守っていることを、言葉にして伝えます。
「この子はこういう服が好きなんだね」、
「お母さんに着せてもらって、○○ちゃん(女の子のように扱う)は嬉しそうだね」、
「お母さん、○○ちゃん、ピンク色とっても似合っていますね」など。
支える側、関わる側が本人を女の子として自然に扱います。
女の子として扱うことをためらわない姿勢を見せます。
支える側がためらうと、母親やご家族もためらいます。
5. 特定の相談場所をもつ
ご家族と本人は、それぞれに相談場所・人が必要です。
いつも必ず味方になってくれる人、ずっと自分たちを知っていて見守ってくれている人がいることは、とても心強く安心です。
地域の方たちとの関わりや、所属園・学校との関係での悩みが多いでしょう。
身近な地域で相談できる場所(母子保健や幼稚園・保育園)か、あるいはカウンセリングを専門にする場所があるとよいでしょう。
どちらもあると、より心強いです。
今は本人には必要ないかもしれませんが、ご家族、特に母親は必要とするでしょう。
少しずつ顔見知りになり、みんなで育てていきましょうということをお伝えします。
「ほかのご家族はどう思っていますか?」
「この子はどんなことが好きですか?そういうとき、戸惑いますよね。」
と寄り添いつつ、母親を継続的に支援することにつなげます。
母親は、積極的に相談はしないかもしれません。
ご家族にとって悩みが深刻なほど、自分からは相談できないものです。
こちらから(あるいは園で)、折々に気にかけていることをお伝えしましょう。
楽しい話題ももちろん加えて、あまり深刻になりすぎないようにすることが大切です。
性別の話題は重要ですが、本人の成長のすべてではありません。
成長の一部、一側面です。
その他にも、こんなことができるようになった、伸びたなど、本人の成長をお互い喜び、共有しましょう。
6. 情報提供
ご家族へこんなケースがあったよ、当事者の会での体験談(ネット)、テレビ番組、パンフレットなどをご案内します。
この子だけでなく、他にもあること、一人だけではない、ということを それとなくお知らせします。
====================================
必要のないこと、段階によってまだ取り組めないこともあります。
すぐにすべてやるのではなく、少しずつがよいです。
このやり方がすべてではないです。
正しいかどうかもわかりません。
他にも手立てがあると思います。
ご家族やご本人の様子を見ながら、どのように関わればいいか、お手伝いする側との関わりの中で小出しにしていけばよいと思います。
こうした子が、みんなとともにすこやかに育ちますように願って。
そして、こうしたご家族があたたかい気持ちで安心してお子さんを育てられますように。