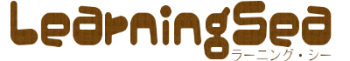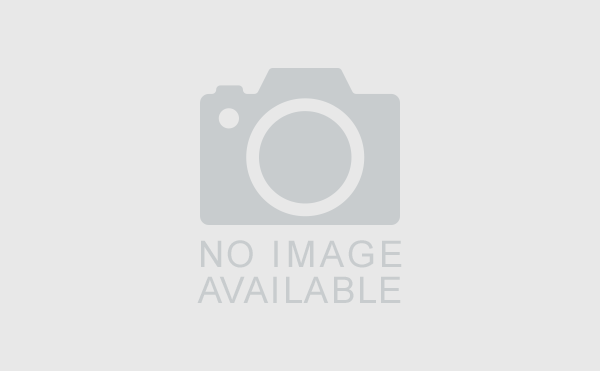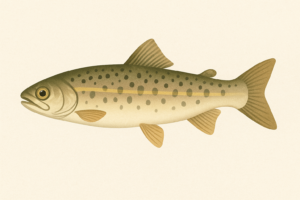【第1回】岩魚の知られざる生態と減少の背景 🐟🌊(映画『ミルクの中のイワナ』を観て)
8月17日日曜日。映画『ミルクの中のイワナ』を観てきました🎥
美しい動画とスタイリッシュな編集、音楽で70分間、たくさんの印象的な知識を得られました。
今日はまず、イワナの生態と減少の背景についてシェアします。
🐟 山女魚でも鱒でもない、「岩魚」という存在
イワナは川魚の代表格のひとつ。でも実は――
-
山女魚(ヤマメ)とは違う
-
鱒(マス)とも違う
**「イワナはイワナ」**という、独自の魚なんです。
しかも面白いのは、全部が川に留まるわけではなく、海へ下り、再び川に戻るイワナがいること🌊➡️🏞️
海に出ると圧倒的に餌が豊富で、成長のチャンスを得られる。自然のしたたかな生存戦略ですね。
🦗 陸上昆虫を食べる不思議
映画で最も印象的だったシーンのひとつ。
イワナの胃の中を調べたら――水中昆虫よりも 陸上昆虫 がたくさん出てきたのです!
ある時期にとくに多かったのは「カマドウマ」🦗。
でも、ただ偶然落ちてきたのにしては多すぎる…。
ここで登場するのが、寄生虫の「ハリガネムシ」🐍
-
ハリガネムシはカマドウマの体内に入り込み
-
宿主を操り、水の中に飛び込ませる
つまり、イワナは寄生虫が操った昆虫を餌として得ていたという仮説!
自然の仕組みが連鎖して、イワナの命を支えている…そんな神秘を感じました。
これはワクチンに入っているハリガネムシにも通ずるかもしれません。
⚖️ 放流という方法の限界
一方で、イワナの数は減少しています。
漁業組合は「魚を増やす義務」があるため、ここ30年以上「放流」という方法を続けてきました。
けれども、この放流には大きな課題があります。
-
養殖されたイワナと在来種が交雑し、川ごとの固有のDNAが失われる 🧬
-
養殖イワナは川の流れを経験していないため、自然環境で生き残れない 💧
結果として「増やしているはずなのに、減っていく」という矛盾が生まれているのです。
🤔 「守る」ってどういうこと?
映画の語りの中で、何度も出てきた言葉――それは「イワナを守る」。
でも、本当に私たちは守れているのでしょうか?
-
川をせき止めたのは人間
-
ダムを作ったのも人間
-
放流という方法を選んだのも人間
むしろ、イワナを追い詰めてきたのは私たち。
映画を観ながら、そんなことを考えずにはいられませんでした。