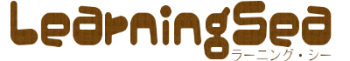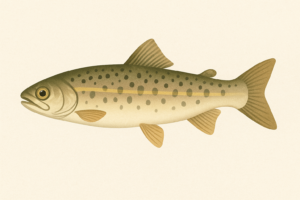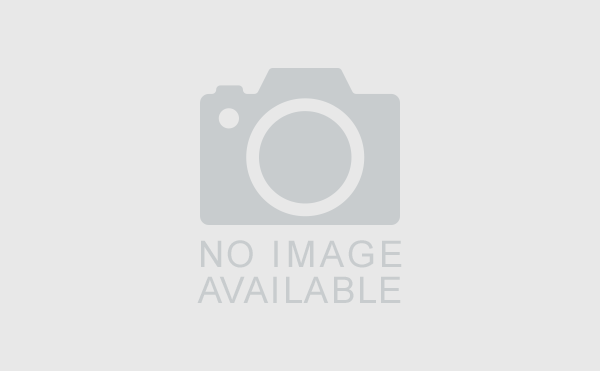【第2回】映画『ミルクの中のイワナ』私たちが🐟イワナを守る??
前回の記事では、イワナの不思議な生態と放流の問題について書きました。
【第1回】岩魚の知られざる生態と減少の背景 🐟🌊(映画『ミルクの中のイワナ』を観て
今回はもっと踏み込んで――
「じゃあ、どうやってイワナを守るのか?」
映画が投げかけた問いを、私なりに熱く語りたいと思います。
🥚 放流よりも「命をつなぐ」方法
イワナを増やす方法は、放流だけではありません。
例えば、イワナが卵を産める場所を人の手でつくること。
イワナはヒレで砂利をかき分け、石の間に卵を産みつけます。
でもダムや堰で遡上が妨げられると、産卵場所はどんどん限られていく。
だから人が「産卵床」を用意してあげることは大切。
けれども――地味でお金もかかる。派手さのある放流イベントと違い、新聞にも取り上げられない。
“地味だけど本当に必要なこと”を、私たちはどこまで選べるのか?
👥 漁業組合の現実
映画では漁業組合の苦悩が繰り返し描かれていました。
-
チケット収入が入らない(買う人が少ない、どこで買えるか分からない)💸
-
組合員は高齢化、若手がいない👴
-
義務はあるけど、権限はない⚖️→遊業券を買ってただの釣り人の方がいい!
「川を守りたい!」と思っても、制度や現実が足かせになっている。
川を見守る人が減り続けている今、この問題は魚の数以上に深刻でしょう。
🌊 自然の力「シフティング・モザイク」
救いのように紹介されていたのが、自然の力。
洪水や川の地形変化によって、新しい産卵場所が生まれる現象を「シフティング・モザイク」と呼びます。
一見すると災害。でも実は、自然は自分でバランスを回復する力を持っている。
人間が手を出す前から、ずっとそうやって命がつながれてきたのです。
🐟 北海道の然別湖(しかるべつこ)が示す希望
映画の中では、北海道のある湖の成功例も紹介されていました。
-
禁漁にした
-
期間を制限した(5〜10月のみ)
-
人数を制限した(予約制)
-
釣っても全魚をリリースする
この「レギュレーション」によって、激減したイワナが復活したそうです。
数字で見ると希望が湧いてきますよね✨
でも同時に、日本の川は長く複雑で、水資源豊富な日本では川と隣り合わせて生活するので、管理することがほぼ不可能。
「同じ方法がそのまま通用するわけじゃない」という現実も突きつけられます。
🔥 「守る」って誰のため?
映画を観ていて、何度も語られた言葉――「イワナを守る」。
でも私は思いました。
-
ダムを作ったのは誰?
-
堰を築いたのは誰?
-
放流を選んだのは誰?
イワナを危機に追い込んだのは、私たち人間です。
だから本当は「守る」なんておこがましいのでは?
むしろ、イワナが私たちを守ってくれているんじゃないでしょうか。
川とともに生きる文化、水の恵み、食の豊かさ…すべてイワナとともにあったからこそ、私たちも生きてこられたのです。
🇯🇵 イワナと日本社会が重なる
映画を観ながら、私はふと日本の「移民問題」と重なると感じました。
-
人口が減っているから「外から人を入れればいい」
-
日本人でさえ減る劣悪な環境で、海外から来る人は心身が健康に根付くのか?
これは、養殖イワナを放流しても定着しない状況と同じでは?
数を増やせばいいわけじゃない。
本当に大事なのは「環境」と「つながり」をどう守るか。
映画を通して、日本の社会そのものを見せられた気がしました。
🌱 最後に
「イワナを守る」――いえ、むしろ私たちがイワナを含む自然に守られているのかもしれない…
私たちの立場は逆転します。
イワナに守られているのは、私たちのほうではないでしょうか。
そして、護岸工事、治水工事をするところから、イワナを含む川に住むあらゆる虫、草、魚、鳥、爬虫類、両生類などの動植物の生き様を私たちは見ていくことなのではないでしょうか。