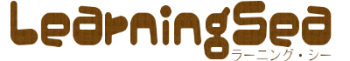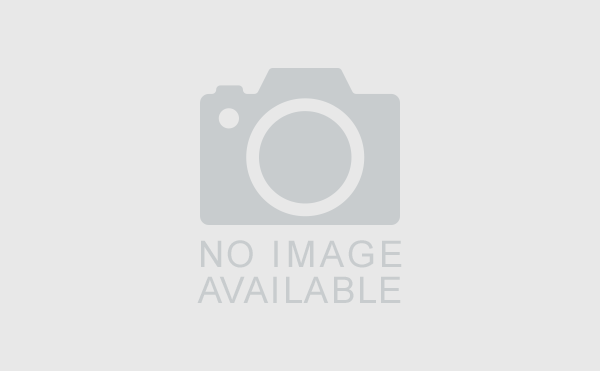感覚統合と「原始反射統合」の決定的な違い〜そして子どもの遊びとは?
「感覚統合」
トランポリンや平均台を使った運動によって、五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)に加えて、前庭感覚(バランス感覚)や固有受容感覚(体の位置感覚)などを含めたあらゆる感覚情報を脳が整理して、上手に使えるようにすることです。
「原始反射の統合」
反射的な言動や振る舞いをしないですむように、モロー反射やガラント反射、足底反射など、さまざまな原始反射を抑制下におくための運動や感覚刺激を使ったアプローチです。
2つの決定的な違い
原始反射統合に使う動きや感覚刺激を、「感覚統合」でも使っています。
じゃあ何が違うのか?
私が考えるに、
「反射を引き起こして、的確な運動や感覚刺激を与えるのか、そうでないのか」
です。
「感覚統合」では、平均台やブランコを使って、緊張性迷路反射やモロー反射、手掌把握反射などを引き出すでしょう。
私は「感覚統合」がもったいないと思うところは、
- 狙って原始反射を引き起こしていないこと
- 原始反射を統合する的確な動きをしないこと
です。
この2つのセットがめちゃくちゃ大事なんです。
もちろん手順がありますし、どの原始反射をどのように引き起こし、どのように運動・感覚刺激でアプローチするか?ということが発達
の知識として必要です。
それを学べるのが、
疑似発達障害ケア講座の「反射1・2(講師:カイロプラクター)」や
私が原始反射を学んだのは、
リズミック・ムーブメント・トレーニングです。
そちらもいいですね👍
他にもBBITなどあります。
最近は、ニューロコネクト・ジャパンの機能神経学の小児ケアシリーズがめちゃくちゃ熱いです。
子どもたちの遊びと原始反射
原始反射統合アプローチの知識がなくても、昭和の時代までは十分に子どもが発達してきました。
平成、令和と難しくなってきた理由は何でしょうか。
なぜ、昭和までは子どもは遊びの中で十分に発達してきたのでしょうか。
その答えは、
「原始反射統合アプローチを遊びの中でやってきたから!」
です。
「反射を引き起こして、的確な運動や感覚刺激を与えるのか、そうでないのか」
これにつきます。
私がこれまで学んだ中では、発達支援に「原始反射」のアプローチ方法は必須です。
Youtubeにもたくさん動画が上がっていますし、本間良子先生と本間龍介先生のご著書もとても役立ちます。
子どもたちの笑顔を心より願っています。