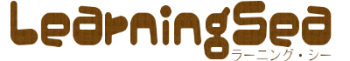癇癪・パニック時は“関わらない支援”は本当に正解なのか?
◆ ペアレントトレーニングで「関わらない」が推奨される理由
ペアレント・トレーニングでは「かんしゃく(感情爆発)」や「パニック」に対して 大人が反応しすぎないこと が大切だとされます。
その背景には、次のような考え方があります:
-
大人が感情的に反応すると、火に油を注ぐことになってしまう
-
なだめたりご褒美を与えることで、「泣けば得られる」と誤学習させてしまう
-
結果的にパニックの頻度や激しさがエスカレートしていくリスクがある
-
専門家ではない親が過剰に介入することが、かえって家庭内ストレスを増やしてしまう
- 関わる親自身が癇癪を起こしている子どもに関わる余力がない対面していることが辛い
つまり、「関わらない」という対応は、子どもを突き放すためではなく、親と子の両方を守るための知恵なのです。
◆ それでも「関わらない」は本当に適切なのか?
子どもがなぜできないのか分からないときに、
できませんというだけで、これをやらなきゃだめというだけで、
怒って泣いている子を放置するのは虐待じゃないのか?
この感覚は、実は多くの支援者や保護者が心の中に抱えている違和感です。
🌱 「関わらない」には前提がある
本来、「関わらないで見守る」ためには、次のような土台が必要です:
-
その子が「落ち着ける」力を少しでも持っていること
-
パニックのあと、安心して戻ってこれる関係性があること
-
大人が「今は関わらないほうがいい」と判断できる根拠があること
しかし現実には、
-
そもそも「落ち着く力」がまだ未発達の子どもも多く、
-
「関わらない」まま終わってしまい、安心できる場につながらない という状況がしばしば起こります。
この状態で「関わらない」を続けると、見捨てられ体験や無力感の学習につながってしまい、悲しいことに「心理的虐待」に近いダメージになってしまう可能性があります。
もちろんあたたかく子どもを迎える方もおられるでしょう❤️
そうでない療育の場も目にしています。
大人も人間なので、ストレス耐性には限りがあります。
◆ では、どうすればいいのか?
「関わらない」と「突き放す」の間にある、第三の選択肢を模索することが大切です。
例:見守りつつ、存在で支える
-
遠くから見守るけれど、視線はそらさない
-
そばにいるけど声をかけず、静かに寄り添う
-
落ち着いたタイミングで、「嫌だったんだね」「〜したかったんだよね」と受け止める
例:子どもの状態を読むスキルを育てる
-
「できない」のか「やりたくない」のかを見極める
-
感情と言葉を一致させる練習を、落ち着いている時間帯に行う
-
「気持ちの折り合いのつけ方」を小さな成功体験で育てていく
◆ 支援を進化させる
「マニュアル通りでは心が痛む」「この子の本当の声を無視していないか」という視点は、現場の支援をアップデートする大切な視点です。
「ペアレントトレーニング」は大きな助けになりますが、それが万能ではなく、子どもと家庭の個性に合わせて柔軟に使っていくことが必要だと考えます。
現場にいたSTの先生は発達特性で癇癪が起きているから、静かになるまで待っていた方がいいと言いました。
私は、発達特性ではなく栄養欠損や副腎疲労でこういうことが起きていると思うと話したところ、「そうなんですね」とスルーされました。
発達特性でこんなにも泣き叫ぶものでしょうか。
そんな状態の子どもを専門家は見慣れすぎて、発達障害にしか見えなくなっているようです。
そう完結すれば、扱いやすくなるからです。
しかし、そう完結してしまえば背景や手立てをそれ以上、探さなくなってしまいます😢