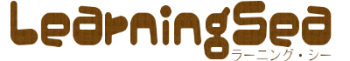音に敏感な子どもたちへ 〜原始反射との関係を探る〜
「うちの子、ちょっとした音にもビクッとして集中できないんです」「背中がそわそわして座っていられないみたい」 そんなお悩みを持つ保護者や先生方に、今回は“原始反射”の視点から「音」と「からだ」の関係を紐解いてみましょう。
◆ 原始反射とは?
赤ちゃんが生まれつき持っている無意識の動き(反射)で、成長とともに自然に統合されていきます。 しかし、何らかの要因で統合がスムーズに進まないと、学習や感覚処理、行動面に影響が現れることがあります。音への反応と関わりが深い反射たち
🔹 モロー反射(Moro Reflex)
突然の大きな音や刺激に対して「ビクッ」と全身で反応する反射。 統合が未完了だと、予期しない音に極端に驚きやすく、常に警戒モードで落ち着かない状態が続きます。🔹 恐怖麻痺反射(Fear Paralysis Reflex)
モロー反射よりも原始的な“フリーズ反応”。 小さな音に対しても心身が緊張し、固まったように動けなくなったり、内向的・回避的な傾向が見られます。🔹 脊椎ガラント反射(Spinal Galant Reflex)
背中の左右を触ると、体をくねらせるように反応する反射。 統合されていないと、背後や側面からの音の振動・刺激に過敏になり、そわそわと落ち着きにくくなります。🔄 組み合わせによる特徴的な反応
✴️ モロー反射 + ガラント反射
- 音に驚きやすく、
- 背中への刺激(椅子の背もたれ・背後からの音)にも過敏で、
- 結果的に「座っていられない」「姿勢が安定しない」状態に。
✴️ 恐怖麻痺反射 + ガラント反射
- 音に対する防御反応が強く、
- 急に固まったようになる or その場を離れようとする、
- 社交的な場面でも回避的・不安定な様子が出ることがあります。
✴️ ATNR(非対称性緊張性頚反射) + ガラント反射
- 頭の動きにより体が左右に引っ張られるような動きが出て、
- 音のする方向へ自然に体を向けるのが困難、
- 左右の音の聞き取りのバランス感覚に偏りが出やすいです。