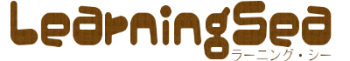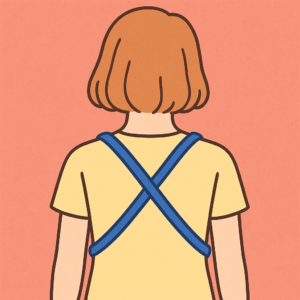子どもの発達は“お口”から!〜顎・口腔の発達と子どもの成長〜
みなさんは「発達障害」と「歯や顎の発達」に深い関係があることをご存じでしょうか?
先日、歯科医でありオステオパスでもある 幸田秀樹先生 の講座に参加しました。司会は進和宏先生です。
その中で、子どもの発達を考えるうえで「👄口腔(がくこうくう:顎と口のまわりの構造)」がどれほど大切かを学びました。今日はその内容をママ向けにシェアしますね😊
1. 子どもの発達と口の関係
文科省の調査によると、小中学生の 約8.8% に発達障害の特徴があるとされています。
幸田先生は「脳の発達」と「👄口の構造」が密接につながっていると説明されました。
-
顎の関節や歯の並びは、呼吸・嚥下(飲み込み)・発音などに影響
-
呼吸が乱れると、脳の発達や集中力にも影響
-
乳幼児期の口の使い方が、将来の学習や行動にもつながる
2. 動物の歯と人間の進化
幸田先生は動物の歯の研究も紹介してくれました。
肉食動物と草食動物では歯の形や数が大きく異なります。
人間は「肉食に完全には適していない」という点がポイント。
さらに、人類の進化の過程で 直立歩行 を始めたことで、顎や顔の形が変化してきたそうです。
(ネアンデルタール人と現代人の頭蓋骨を比べると一目瞭然!)
3. 顎と成長のタイミング
👄口腔は「三階建ての構造」と表現されました。
-
1階:口と消化器系
-
2階:呼吸器系
-
3階:頭部の神経系
この3つは互いに影響し合いながら発達していきます。
特に注目なのは 足の親指の発育。
「足の親指が強い子ほど脳の発達が良い」という研究もあり、全身の成長と口の発達がリンクしていることがわかります。
4. 呼吸と母乳育児の大切さ
顎の発達で最も重要なのは 呼吸。
口呼吸から鼻呼吸へ移行することが脳の発達に直結します。
幸田先生は、上顎を広げる治療(Rapid Maxillary Expander)によって呼吸が改善した例を紹介しました。
また、母乳育児の重要性についても言及。
-
生後0〜6か月は完全母乳が理想(WHO推奨)
-
6か月〜2歳以上は母乳+離乳食
-
母乳育児が短い、指しゃぶりや長い哺乳瓶使用は顎の成長に悪影響
5. 出産後の赤ちゃんの👄口腔と哺乳瓶
講座では「出産後の赤ちゃんの👄口蓋や頭蓋骨の変形」についての質問も出ました。
-
出産時の吸引分娩などで変形がある場合は、6か月までに治療するのが一般的
-
母乳を吸う力が弱いときは、「出にくい哺乳瓶」を使うと、母乳に近い口の動きができてよい
-
長期間の哺乳瓶や指しゃぶりは、顎の発達に悪影響
6. 顎のズレと全身への影響
日本人に多いのは「下顎が後ろに下がるタイプ」のズレ。
これにより歯列や噛み合わせが乱れ、頭痛や肩こり、全身の痛みにもつながることがあるそうです。
咀嚼(噛むこと)は、単に食べ物を砕くだけでなく、脳や体全体を整える大切な働きを持っています。
7. 顎と脳のつながり
幸田先生はさらに、顎の発生や成長についての研究も紹介。
-
顎の成長には上顎と下顎の相互作用が関わる
-
母乳育児がそのバランスを整える役割を持つ
-
顎関節にかかる力が、脳の前頭葉の働きにまで影響する可能性 がある
つまり、顎の発達は「見た目や歯並び」だけでなく、脳の機能や発達にも深くつながっているんです。
8. 👄口腔機能の4つのカギ
最後に幸田先生が強調されたのは、👄口腔機能の基本。
-
唇をしっかり閉じられる
-
舌が正しい位置にある
-
飲み込みがスムーズ
-
噛む力が十分
この4つが整うと、歯並びだけでなく 全身の健康や発達 が促されるのです✨
まとめ
今回の講座を通じて、「歯や顎は単なる“口の問題”ではなく、全身の発達や脳の働きと深くつながっている」ことがよくわかりました。
-
母乳育児や呼吸の習慣が顎の発達を左右する
-
足の親指や姿勢も👄口腔と関係している
-
顎や歯のバランスは脳の働きにも影響する
-
正しい👄口腔機能が子どもの健やかな発達を支える
毎日の小さな習慣が、子どもの未来をつくります🌱