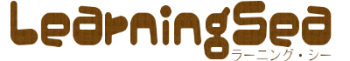疑似発達障害ケア上級講座完結!
✨疑似発達障害ケア・上級講座 完結報告✨
10月5日(日)、全国の専門家・支援者が集い「疑似発達障害ケア 上級講座」の最終回が開催されました。
各分野の講師陣による臨床報告とケースディスカッションは、発達支援の実践現場に直結する学びとなりました。
🧠 臨床事例①「ビジョン(視覚機能)と行動」
講師:松本康宏先生
視覚情報処理の困難が、姿勢制御・注意集中・頭痛などの身体症状と関連することを、小学生の症例を通して解説。
ブロックストリングスや視覚追従・跳躍運動の評価をもとに、右後頭部の緊張と小脳系の関与を考察。
さらに、運動刺激+触覚・聴覚刺激を組み合わせることで神経可塑性を促すアプローチを実演。
学校現場での「視覚機能不全の早期発見」と「運動による介入の意義」が共有されました。
🍎 臨床事例②「栄養と神経機能」
講師:石原英和先生
肝炎や慢性疲労を背景にした10歳児のケースを通して、ミトコンドリア機能低下・タンパク質消化不良・ビタミンB群不足など、
生化学的側面からの行動理解を提示。
特に、自閉スペクトラム児の血液検査に見られた「カルニチン不足」「ビタミンB6・B2欠乏」「神経伝達物質低下(ドーパミン・セロトニン系)」をもとに、
学習意欲・集中・情動調整への影響を分析しました。
栄養療法と感覚統合、体幹トレーニングを組み合わせた統合的アプローチの必要性が強調されました。
👣 臨床事例③「集団療育と発達支援プログラム」
講師:福田あかり
ダウン症児・低緊張児の集団療育の実践を通して、原始反射の統合と体性感覚の発達を促す支援法を紹介。
「脊椎散歩」「足裏伸ばし」「ハイタッチウェーブ」「大根抜きゲーム」など、
姿勢保持・重心移動・呼吸統制を遊びの中で促す体操プログラムを実施。
乳幼児期の低緊張と口腔機能の発達が、後の多動性や注意調整に影響することを説明しました。
学校・療育現場での集団活動における身体アプローチの意義を再確認する時間となりました。
🌈 臨床事例④「統合的アプローチ」
講師:吉田優也先生
「視覚」「栄養」「身体」「情動」それぞれの要素を横断的に捉え、発達支援を多系統的に統合する視点を提示。
個々の発達課題を“症状”ではなく“神経発達の偏り”として理解し、
環境調整・感覚刺激・身体運動・食事改善を連動させる実践的な方策を共有しました。
🪞今回の上級講座では、
学校での“行動上の困りごと”を神経・代謝・身体・環境の多層構造で理解する視点
体験に基づいた神経発達支援(原始反射・ビジョントレーニング・運動療法・栄養調整)の実際
が学びの中心となりました。
子どもの行動の背景には、**「脳の使い方」「感覚の受け取り方」「身体の反応性」**があります。
観察力と身体理解を磨くことで、教室での支援の質は確実に変わります。
ご参加くださった先生方、臨床家の皆さま、心より感謝申し上げます。
#発達支援 #疑似発達障害ケア #視覚機能 #感覚統合 #原始反射統合 #栄養と発達 #神経可塑性 #学校教育 #LearningSea